
広島東照宮 鳥居 |

広島東照宮 |
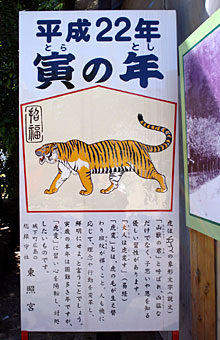 |
東照宮の建造物(広島市指定重要有形文化財)
(現地案内文より)
東照宮は慶安元年(1648)、徳川家康を祭るため、時の藩主によって建立された。当時の建物のうち本殿、拝殿は昭和20年の原爆により焼失したが、残った唐門などから当時の建築様式をしのぶことができる。唐門(からもん)日光東照宮の様式にならう。装飾的彫刻に時代的特色がある。翼廊(よくろう)唐門とは対照的に和様を主体とした簡素な構えである。本地堂(ほんじどう)もと本地仏を安置。蟇股は桃山〜江戸の移行期の形式を示す。手水舎(てみずしゃ)板蟇股は室町。虹梁や拳鼻は江戸期の代表的彫法を用いる。御供所(ごくうしょ)外観は江戸期の書院、内部は所々に室町時代の様式を残す。脇門(わきもん)豪壮で簡素な感じは戦国時代の遺風である。 |
 手水舎 手水舎
「総朱漆塗り」、「蛙股の月と兎」など桃山時代の建築様式をよく伝えている。
東照宮唐門及び翼廊は工事中でした。
 広島東照宮のホームページ 広島東照宮のホームページ |

 |

ジャンボ釜(現地案内文より)
容量:2160リットル(ドラム缶約12本分) 重量:1トン 材質:鋳鉄
古代から中国山脈に産する砂鉄は「鈩技法」により玉鋼として日本刀に、一方鋳鉄として鍋、釜、風呂釜の製造に用いられた。この大羽釜はまわし形という手法で型が作られ鋳造された。今ではこの技法を伝える人は無いと云われる。かつて全国で風呂釜の八割を生産して鋳物王国といわれた広島の伝統を伝えるため、市内可部町の大和重工(株)で復元され昭和61年当宮に寄進された。 |

ニ葉山にはフクロウがいます。このセンダンの木(樹齢約80年)のほら穴には毎年フクロウが産卵し、多くの若鳥が巣立ちましたが、平成18年突然木が枯れて伐採、「梟の巣穴」として保存しました。 |

楓樹(ふうのき) 徳川八代将軍吉宗ゆかりの秘木で皇居吹上御所の庭園に生存、その種子を昭和天皇が日光東照宮に下賜、育成し成木となり、当宮に二本おくられました。 |

本地堂 |

北側から見た東照宮 |